スガシカオ(2016)『THE LAST』
単純接触効果というものをご存知だろうか。人は数多く見聞きする対象に好意や関心を抱きやすいという考え方のこと。最初は絶対にありえないと思っていた多部未華子が、いつの間にかやたら可愛く見えてくるという、例のアレだ。同様にテレビ番組のタイアップ曲が持つ浸透力も、いまだバカにできないものがある。もともと好みのアーティストではなかったのに、毎週欠かさずの『プロフェッショナル 仕事の流儀』は、私のスガシカオに対する親近感をピークにまで高めてしまった。同じ曲を一年に50回も聞き続けたら誰だってそうなる。そんな経緯で吸い寄せられるように買い求めた『THE LAST』、これが予想以上に大当たりだった。「良質な曲作りに定評のあるシンガーソングライター、ただしプロダクションはオーソドックスで面白みに欠ける」。そんな先入観がこれでもかと裏切られていく。M1〔ふるえる手〕こそイメージ通りだったが、M2〔大晦日の宇宙船〕が早々にヘン。けれん味が強いというか、ギターもキーボードもトゥーマッチでメリハリがありすぎる。極めつけはコーラスに重ねられた、オッサンによる珍妙な叫び声。何が楽しくてこんなアレンジを? マリリン・マンソン『メカニカル・アニマルズ』を隣に並べたくなるような、やたら壮大でシアトリカルな爆笑展開。M3〔あなたひとりだけ 幸せになることは 許されないのよ〕に移ってもしつこく野太く断末魔が響きわたり、脱力すること請け合いである。一方、ベースラインは近作のナイン・インチ・ネイルズを思わせる鳴りでストレートに格好よく、巧妙にフォーカスを絞らせない。このキッチュとシリアスの混在する居心地の悪さをどう捉えるかで、本作の評価が分かれそうだ。私はそんな凸凹がどうやって組み上がっているんだろうとあっちこっちから眺めまわしているうちに、完全に虜になってしまった。なお、スガシカオは2015年のベストアルバムにディアンジェロとファンクストラングを選出している(「MUSICA」2016年1月号)。ファンクストラングといえば90年代から活躍するドイツのエレクトロニック・デュオだが、この辺りへの関心が本作のユニークなプロダクションに寄与しているということなのだろう。
山本さほ(2015〜)『岡崎に捧ぐ』
1985年だ。筆者もピンポイントで作者と同い年の生まれ。なので自然、出てくるアイテムや出来事にいちいち懐かしさが止まらない。シンクロできすぎて、例えばこれを1975年生まれの人や1995年生まれの人が読んだらどう感じるのか、心配になってしまう。はたして面白いのか? じゃあ仮に、1975年や1995年生まれの人が書いた『岡崎に捧ぐ』的なものがあったとしたらどうだろう。それはもう、ぜひ読んでみたい。自分たちが「たまごっち」だの「バトルえんぴつ」だのに費やした途方もないエネルギーを、10才上の、10才下のジェネレーションはどこへぶちまけていたのか。それをこの『岡崎』レベルの濃密なリアリティで味わってみたいと切に思う。そして実は、そんな取り留めのない小並感(しょうなみかん)にこそ、小学生や中学生だった頃の自分と現在との決定的な線引きを見出したりもする。作中には「ゲームボーイ」のエピソードが出てくる。「ゲームウォッチ」のような単一ソフト搭載機はそれ以前にもあったのだけれど(いまゲームウォッチを改めて画像検索すると、外形が完全に「ニンテンドーDS」でびっくりしますね)、外に持ち運べて、カートリッジでソフトを交換できて、というのはほんとうに画期的だった。それが「ゲームボーイポケット」が出て「ゲームボーイカラー」が出て、次々に更新されていく。だから当時の自分はこう思っていた。〝いま・ここ〟こそがもっとも素晴らしいのだと。ファミコンとPCエンジンでしか遊べなかった人たちはなんて可哀想なんだろうと。中学に入って短冊CDを買うようになってからも、ベースの考えは変わらなかった。とにかく〝いま〟売り出されている音楽が一番かっこいいし、〝ここ〟が最先端。そういう激しい思い込みは、もちろん徐々に修正されていくことになるのだが、ダメ押しはカラオケボックスだったような気がする。大学生になり社会人になり、同世代でカラオケにいけば結局は90年代のヒット曲を歌いまくることになった。ミュージックステーションではジュディマリが懐メロとして取り上げられていた。そのとき、あっと思った。10才上には10才上の「たまごっち」が、10才下には10才下の「バトルえんぴつ」があり、自分たちはそのワンオブゼムにすぎないのだと。書いてしまえば当たり前すぎてくだらないのだけれど、腑に落ちる、というのはどこまでも個人的な体験でしかない。それ以来、古臭いと敬遠していた過去の作品群が、少しずつ親しみを持って迫ってくるようになった。拠って立つ足場の底が抜けたのだ。そこから先は、自由に動き回ることができる。人はどんどん忘れないと生きていけないので、ちょっと前に抱いていたフィーリングをいとも容易く思い出せなくなってしまう。あんなに頑迷だったつい昨日の自分をまるで別人のように扱っていた。『岡崎』を読まなければ、ずっとそのままだったに違いない。そういうわけで、私はいま、どちらかというと年の離れた世代による『岡崎』が読んでみたい人間になっている。
星野源(2015)『YELLOW DANCER』
俺、すごいことに気づいちゃったかもしれない。「なに? どうしたの?」 星野源ってさ、たぶん2010年代の小沢健二なんだよ。「はあ」 今までミュージシャンとしての星野源を全然知らなくて。ほぼ唯一の接点が、木皿泉のドラマに出てたのを観たくらいだったんだよね。『昨夜のカレー、明日のパン』、仲里依紗が主演の。それだって七年前に死んじゃった夫の役だから、ほとんどセリフがなくて。その時の印象は薄かった。ミュージシャンなのは知ってたけど、あんまり縁のない人だって食わず嫌いで済ませてたんだよね。で、またドラマ絡みになっちゃうんだけど、フジの『心がポキッとね』の主題歌が〔SUN〕だったじゃない。メロディのキャッチーさは言うまでもないとして、コーラス終わりに入ってくるアナログシンセのジリジリした質感が妙に格好いいと。そこで初めておおっと思って、気になりはじめた。頭から聴き直すと、イントロがまさにそのシンセのズズーって音なんだよね。意識しだしたら、星野源、ほんとうにいたるところで出くわす出くわす。本屋じゃ平積みだし、バラエティ番組でもみかける。文字通りのマルチな活躍ぶりだと。そして、文化系女子に熱狂的に愛されている(笑)。そのあたりで頭をよぎりました、彼のことが。全盛期のオザケンとその周囲って、もしかしてこんな感じだったのかもと。ふっふっふ。「……一応、終わりまで聞こうか」 二人ともグループでミュージシャンデビューして、ソロシンガーへ転身というキャリアパス。そこにきて今回のアルバムでしょ。ブラックミュージックのオリジナルな翻案が評判の『YELLOW DANCER』。一方の小沢健二も『犬は吠えるがキャラバンは進む』から早々に黒くて、『LIFE』はスライ&ザ・ファミリー・ストーンへのリスペクト、さらにブラック路線の決定打として『Eclectic』がある。もうオザケンにしかみえないよ。ね? 「延々しゃべらせといて悪いんだけど、『星野=小沢』説って、かなり前から言われてるよ」 え……そうなの? 「うん。しかも一人や二人じゃなくて、けっこうみんな言ってる」 そ、そっか。やっぱり考えることはみんな同じなのかもね。「オレはむしろ、今回改めて、星野=細野晴臣なんだなって思ったけど」 ああ〜、細野さんって星野源のタニマチだもんね。日経ビジネスの特集記事でもベタ褒めしてたし。「『YELLOW DANCER』のジャケット自体、YMOへのオマージュじゃん。間違いなくファースト(US版)を意識してる。ハンガーに着物引っかかってるよね」 アレそういうことなんだ!? 全然気づかなかった。「まずそうだと思うよ。で、YMOといえば、結成当初の青写真になったのがマーティン・デニー〔Firecracker〕のカバーなわけだけど、原曲を収録した彼の『Quiet Village』というアルバムに、その名も〔Sake Rock〕という曲が入っている」 えー! あのジャケからYMO経由で、バンド名の由来までたどれちゃうんだ(笑)。音楽性としても細野テイストあるの、今回? 「あるある。M5〔Soul〕なんかまさにそうで。トロピカル三部作あたりの細野、思いっきり」 良かったよね、〔Soul〕。コーラスのベースラインがジャクソン5の〔I Want You Back〕っぽくて最高。アルバムで一番好きかも。細野晴臣ちゃんと聴いてみたくなってきた。「一枚通して聴くと、星野源、そりゃ人気出るわっていう納得の仕上がりだったね」 文筆業、エッセイなんかも面白くてまたニクい。下ネタ全開の愛されキャラといえば、先人は福山雅治か。「不謹慎かもしれないけど、病気から奇跡のカムバックストーリーはミスチルの桜井和寿だし」 物語性も備えていると。まさに全方位対応。しばらくは星野源の時代が続くね。こりゃもうライブ観に行くしかないよ。

- アーティスト: 星野源
- 出版社/メーカー: ビクターエンタテインメント
- 発売日: 2015/12/02
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (5件) を見る
ロロ(2015)『いつだって窓際であたしたち』@STスポット横浜
ロロは今回、新たに「いつ高シリーズ」をスタートさせた。舞台となる〝いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校〟の名称は、小沢健二の楽曲にあやかったものである。高校演劇のフォーマットに即して作られていることがシリーズの特徴だ。すなわち「上演時間は60分以内、装置設置撤去30分以内とする」などの制約を、進んで受け入れているのである。主宰の三浦直之によると、シリーズのテーマは〝まなざし〟だという。第一弾の『いつだって窓際であたしたち』は、こんなふうに始まる。シューマイと呼ばれる男子がじぶんの席にもどってくると、知らない女子がそこにすわっている。寝ている。シューマイは呆然と女子をみつめる。教室から外へと向けられるまなざしもある。女子は校庭を一望できるその席が気に入ったらしく、そこから校庭のトラックを走りまわる「たろう」という別の男子のことをみている。シューマイもちらちらと窓の外をながめる。どことなく『桐島、部活やめるってよ』を思わせる場面だ。吹奏楽部員で地味なタイプの沢島(大後寿々花)は、教室で前の席にすわる宏樹(東出昌大)に思いを寄せている。けっきょく彼女の思いが叶うことはなく、沢島と宏樹が直接には視線を交わすことのないまま、映画は終了する。しかし、ある意味ではふたりがそれを交えていたといえるシーンがひとつだけあった。ホームルームの時間、窓際の席、宏樹がなにげなく外の景色に目をやり、視線の先を沢島が追う。その瞬間、教師の話し声も物音も、数秒にわたりすべて聞こえなくなる。沢島がいつか高校時代を振り返ったとき、思い出すのはきっとこの情景になる。さて、本公演のタイトルには『いつだって窓際であたしたち』とある。それにつづく言葉はどんなものだろう? たとえば、いつだって窓際であたしたちは「おしゃべりしている」、という言い方は、文法的になんら問題がないとしても、どこか収まりが悪い。それよりは、いつだって窓際であたしたちは「おしゃべりしていた」、のほうがずっとしっくりくる。三浦はタイトルに、あとから振り返ったときの高校生活、というニュアンスをまとわせている。そう考えればシリーズの命名にあたり小沢健二が召喚されたことも、偶然とは思えない。『日本のロック名盤ベスト100』のなかで川﨑大助は、〔愛し愛されて生きるのさ〕を収録した『LIFE』についてこう語っている。「第一の特徴は、やはり、過去の名曲や名演の引用や模倣の数の多さだ。まずアルバム・タイトルそのもの、タイトルやアーティスト名のロゴ・デザインまで、アメリカのスライ&ザ・ファミリー・ストーンの六八年の名盤の「そっくりそのまま」であるところから始まって、曲や詞やアレンジについても同様だった」。1968年。なにかと神格化されやすいこの年は、ロックミュージックにとっても最良の季節だった。社会変革への意志とともに音楽がシェアされていた。1960年代をロックの青春時代とみなすこともできるだろう。小沢はスライの『LIFE』を、理想に満ちていた時代のシンボルとして自身のアルバムに引用した。そして三浦は、ありえたかもしれない(実際にはなかった)青春時代を小沢の『LIFE』に投影する。スマートフォンやグーグルストリートビューといった現代的な小道具のせいでわかりにくくなっているが、『いつ窓』は、失われた過去をめぐる一時間なのである。小沢がスライに、いまでは〝失われたもの〟を感じとったように、三浦が小沢を聴いてそれを反復したように、私たちは『いつ窓』にノスタルジーを覚える。ただし、〝失われた〟という感覚は、それが過去に存在したことを保証するものではない。作中、シューマイがiPhoneでBABYMETALの〔ギミチョコ!!〕を聴いていることから、観客は、舞台が現代であるという印象を受ける。スマホ・グーグル・ベビメタ。だからこそ、終盤でサニーデイ・サービスの九六年の楽曲〔真っ赤な太陽〕が登場したときの違和感には、くれぐれも注意を払いたい。現代の高校生であるはずのシューマイたちが、「なんかCMとか」で聞き知ったらしい〔真っ赤な太陽〕を高らかに歌い上げる。発表年に正確を期すならば、時空が歪んでいる。この瞬間、〝失われた〟感覚のいくらかは、私たちが美化し、新たに創り上げたものだということが強く意識されてくる。青春を扱った明るく楽しい『いつ窓』は、ここにいたって意外な苦味を残すのである。だがそのギャップが良い。このくだりがなければ、作品の魅力は半減していた。ふたたび川﨑の言葉を借りてレビューを終えよう。〔真っ赤な太陽〕が収録されたアルバム『東京』について。強調は筆者が付した。「最大の武器は「架空のノスタルジー」だったか。自ら体験したこともない、六〇年代や七〇年代の空気を、執拗に再現しようとするかのような楽曲とサウンド・プロダクションだった」。
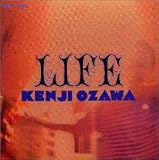
- アーティスト: 小沢健二,スチャダラパー,服部隆之
- 出版社/メーカー: EMIミュージック・ジャパン
- 発売日: 1994/08/31
- メディア: CD
- 購入: 11人 クリック: 1,152回
- この商品を含むブログ (743件) を見る
3776『3776を聴かない理由があるとすれば』
まったく知りませんでした、3776(みななろ)。こんなキテレツな音源がふつうにリリースされていたとは。日本レコード協会によると2014年に発売されたCDの新譜数は15,996点(すべて12cm、シングル・アルバムの合算)。ピークを過ぎたとはいえ、一日あたり約44枚もの新作がフィジカル・パッケージの形態で生まれ続けている。そこへYouTubeや各種ストリーミングサービスが加わってくると、一生かけてもたった一年分の音楽すら消化できないだろうなと気が遠くなってしまいますよね。勢い、定評のある過去の名盤を聴き返したり、気に入ったアーティストだけを追いかけたりといったスタンスに流れがち。3776のファーストフルアルバムは、そんな態度に大いに反省を迫ってくる一枚でした。俺はこんな作品をスルーしたまま2015年を終えてしまったのかと。まず音の外形について。実質1曲目のM2〔登らない理由があるとすれば〕を聴いて、少なからぬ人がこう声を上げたことでしょう。「何だこれ! 空間現代の新作かよ!?」 空間現代は批評家・佐々木敦主宰のレーベル=HEADZに所属する3人編成バンド。そのマスロック的、ポストパンク的傾向でつとに知られています。私はアルバム『空間現代2』所収の〔不通〕というトラックが好きなのですが、すぐ後ろにこっそり〔登らない理由があるとすれば〕が置かれても初聴ならまったく気付かないのではというくらい、ギターの鳴りが空間現代だったのです。ちょっと鼻息が荒くなってしまいました。さて、3776唯一のメンバー・井出ちよのによるヴォーカルが乗ってきて、少しく平静を取り戻します。要するにこれは「目配せ」なんだろうなと。ティーンアイドルにコア/マイナーな音楽を掛け合わせる流行りのメソッド(その最大のスターがBABYMETALでしょう)に対しリスナー側も免疫ができつつあり、「空間現代っぽくて最高!」とか「◯◯へのオマージュがたまらない!」とか、思ってても言いたくない、言ったら負けだ(?)という面倒くさい心理がはたらくのです。たしかに、件のメソッドの応用という観点だけでみると、突出した作品ではないかもしれない(音楽的な面白味は十二分にあるのですが、この界隈のクオリティ=ハードルが上がってしまっている)。では、他のアイドル音楽と『3776を聴かない理由があるとすれば』を分かつものは何か? それはアルバムトータルでの完成度です。収録時間が富士山の標高と同じ3776(秒)という作り込みから始まって、一曲ずつ富士山を登っていくコンセプト。歌詞の言葉選びも「湧玉池」だったり「八合目」だったりと富士にちなんだものがしきりに登場します。そして頂上へ。M19〔3.11〕。そう、あの日の地殻変動で富士山の標高も3776ではなくなってしまった。全体としてチアフルなアルバムですが、それだけではありません。「もっと見とけばよかった ちゃんと見とけばよかった いつもこんな近くで いつも見られたのに」。必聴かと。


